【起業準備中必見!】失業給付の給付日数・金額は?賢く活用し起業と節税両立!
「会社を辞めて起業したいけれど、資金繰りが不安…」 「起業に向けて勉強したいけど、無収入になるのが怖い…」 「失業給付って実際いくらもらえるの? 期間はどれくらい?」
もしあなたが今、そんな悩みを抱えているなら、この記事はまさにあなたのためのものです!実は、起業準備期間中でも「失業給付金」を受け取れる可能性があることをご存知でしょうか?しかも、その給付日数や金額は、あなたの状況によって大きく変わるのです。
私自身も会社を退職後、起業準備中に簿記3級とFP3級の資格を取得し、失業給付を受け取りながら、安心して起業準備を進めることができました。この記事では、私が実際に経験した「起業準備と失業給付の両立術」に加え、あなたが最も気になるであろう「給付日数」と「給付金額」の仕組みを具体的な方法とともに分かりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたは以下の疑問を解決し、資金の不安を解消しながら、自信を持って起業準備を進める道筋が見つかるはずです。ぜひ最後まで読んで、あなたの起業を成功させる一歩を踏み出しましょう!
起業準備中でも失業給付はもらえる!給付日数・金額を理解し賢く活用しよう!
会社を退職し、起業を予定している方でも失業給付(基本手当)を受け取ることは可能です。 ただし、「求職活動を並行している準備段階」であることが大前提となります。
失業給付は、再就職を支援するための制度です。そのため、基本的には「就職したいという意思がある人」が対象です。しかし、起業準備中に必要なスキルアップのための学習や資格取得は、再就職にも役立つとみなされ、求職活動として認められるケースが多くあります。 あなたの努力次第で、給付金を受け取りながら、安心してスキルアップできるのです。
簿記とFPの資格取得が求職活動実績になる理由
なぜ簿記やFPの資格取得が求職活動実績になるのでしょうか。その理由は、これらの資格がビジネスにおいて汎用性の高いスキルを証明するからです。
簿記の知識は、起業する上で必須の知識であるだけでなく、一般企業の経理や事務職、営業職など、多岐にわたる職種で役立つスキルです。 多くの企業が簿記の知識を持つ人材を求めています。
FP(ファイナンシャルプランナー)の知識は、起業後の節税対策や社会保障制度の理解に直結します。 また、個人の資産形成やライフプランニングに役立つため、金融業界や保険業界など、幅広い分野での再就職に有利に働きます。
これらの資格取得に向けた勉強や検定試験の受験は、「再就職のためのスキルアップ」とハローワークに判断され、正当な求職活動として認められます。 私自身も休職期間中に簿記3級とFP3級を取得し、給付を受けながら学びを深めました。
気になる給付日数!あなたの勤続年数でどう変わる?
失業給付を受けられる日数(所定給付日数)は、主に**「離職理由」「雇用保険の被保険者であった期間(勤続年数)」「離職時の年齢」**によって決まります。
ここでは、一般的なケースとして、自己都合退職と会社都合退職(特定受給資格者等)の2つのパターンで、勤続年数に応じた給付日数を見てみましょう。
【失業給付の給付日数(目安)】
| 離職理由 | 被保険者期間(勤続年数) | 給付日数 |
|---|---|---|
| 自己都合退職 (1および3以外の離職者) |
1年以上5年未満 | 90日 |
| 5年以上10年未満 | 90日 | |
| 10年以上20年未満 | 120日 | |
| 20年以上 | 150日 | |
| 会社都合退職 (特定受給資格者等) |
1年以上5年未満 (30歳未満) | 90日 |
| 1年以上5年未満 (30歳以上45歳未満) | 120~150日 | |
| 10年以上20年未満 (45歳以上60歳未満) | 270日 | |
| 20年以上 (45歳以上60歳未満) | 330日 |
※上記は一般的な目安であり、離職時の年齢によってさらに細かく設定されています。
※自己都合退職の場合、給付制限期間(原則2ヶ月または3ヶ月)がある点に注意が必要です。この期間は給付金が支給されません。
※上記は一般的な目安であり、離職時の年齢によってさらに細かく設定されています。 ※自己都合退職の場合、給付制限期間(原則2ヶ月または3ヶ月)がある点に注意が必要です。この期間は給付金が支給されません。
あなたの勤続年数や離職理由によって、最大で330日(約11ヶ月)もの給付期間があることがわかります。この期間を有効活用して、起業準備や資格取得に集中できるのは大きなメリットです。
毎日の給付金額はいくら?年収との関係と上限額をチェック!
次に気になるのが、「1日あたりいくらもらえるのか」という給付金額(基本手当日額)ですよね。これは、あなたの退職前の賃金(年収)**によって決まります。
基本手当日額は、原則として離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割った「賃金日額」に、給付率(45%~80%)**を掛けて算出されます。
基本手当日額の計算式: 基本手当日額=賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率(45%~80%)
給付率は、賃金日額が低い人ほど高く(最大80%)、賃金日額が高い人ほど低く(最低45%程度)なります。これは、生活保障の観点から、賃金の低い方への配慮があるためです。
年収別の基本手当日額(概算)と上限額
ただし、どんなに年収が高くても、基本手当日額には年齢に応じた上限額が設定されています。例えば、令和6年8月1日以降の目安では以下のようになります。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,065円 |
| 30~44歳 | 7,845円 |
| 45~59歳 | 8,635円 |
| 60~64歳 | 7,420円 |
※これらの金額は毎年8月1日に見直されます。
| 年収 | 月収(概算) | 賃金日額(概算) | 基本手当日額(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 約33.3万円 | 約11,100円 | 約5,550円~7,845円 (上限による) |
この年収帯だと、賃金日額によっては給付率が高めに設定される可能性も。年齢によっては上限額に近づきます。 |
| 600万円 | 50万円 | 約16,667円 | 約7,420円~8,635円 (上限による) |
賃金日額が上限額に近いため、年齢に応じた上限額が適用される可能性が高いです。給付率は実質的に50%を下回ることも。 |
| 800万円 | 約66.7万円 | 約22,233円 | 上限額が適用される | 賃金日額が各年齢層の上限額を大きく超えるため、どの年齢層でも「基本手当日額の上限額」がそのまま支給されることになります。例えば45〜59歳なら8,635円が上限です。 |
| 1000万円 | 約83.3万円 | 約27,767円 | 上限額が適用される | 年収800万円の場合と同様、各年齢層の上限額が適用されます。 |
※上記の金額は概算であり、具体的な給付額はハローワークで計算されます。
※基本手当日額の上限額は毎年8月1日に見直されます。
ご覧の通り、年収が高いほど給付額も上がりますが、ある一定の年収からは上限額に達するため、それ以上は給付額が増えない仕組みです。自分の給付額を知ることで、起業準備期間中の生活設計が立てやすくなりますね。
実際に失業給付を受けながら資格取得する具体的な方法
失業給付を受けながら、簿記やFPの資格取得を進めるには、いくつかのステップを踏む必要があります。
退職後の手続きと「求職の申し込み」
会社を退職したら、まずお住まいの地域を管轄するハローワークに行き、**「求職の申し込み」と「雇用保険受給資格の決定」の手続きを行います。この際、「起業も視野に入れているが、再就職も検討している」**という意思をしっかりと伝えましょう。
雇用保険受給者初回説明会への参加
手続き後、指定された日に「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。ここでは、雇用保険の制度や失業認定のルール、今後の手続きについて詳しく説明があります。
失業認定日の求職活動実績申告
失業給付は、原則として**4週間に1回の「失業認定日」**にハローワークへ出向き、前回の認定日以降の求職活動実績を申告することで支給されます。この際に、簿記やFPの検定試験を受験したことを実績として申告します。受験票(受験したことがわかるもの)を保管しておき、提示できるよう準備しましょう。
注意点:ハローワークへの正直な申告が必須
失業給付を受けながら資格取得や起業準備を進める上で、最も重要なのがハローワークへの正直な申告です。
起業準備が進み、開業届を提出したり、事務所を借りたりするなど、「事業を開始した」と判断されるような行動があった場合、その時点で失業給付の支給は停止されます。 その後は、基本手当の代わりに**「再就職手当」**の申請を検討することになります。
もし、意図的に状況を隠して失業給付を受け続けると、不正受給とみなされ、支給停止はもちろん、厳しいペナルティが課される可能性があります。必ずハローワークの指示に従い、不明な点は積極的に相談してください。
まとめ:資格取得と給付金を活用し、起業への道を賢く進もう!
今回は、起業準備中に失業給付を受けながら、簿記やFPの資格を取得する方法、そして給付日数と給付金額の仕組みについて解説しました。
- 起業準備中でも、求職活動を並行していれば失業給付は受給可能です。
- 簿記やFPの資格取得は、再就職にも繋がるため、求職活動実績として認められます。
- 給付日数や給付金額は、勤続年数や年収によって大きく異なりますが、上限額があることを理解しましょう。
- ハローワークへの正直な申告と、定期的な求職活動が重要です。
資金の不安を抱えながらの起業準備は、精神的にも大きな負担です。失業給付という制度を賢く活用し、簿記やFPの知識を身につけることで、あなたは安心して起業準備を進められます。これらの知識は、税理士を目指す私にとっても、そして起業を目指すあなたにとっても、将来の事業運営における強力な武器となるでしょう。
さあ、今日から行動を起こし、あなたの夢の実現に向けて最初の一歩を踏み出しましょう!


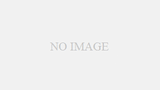
コメント